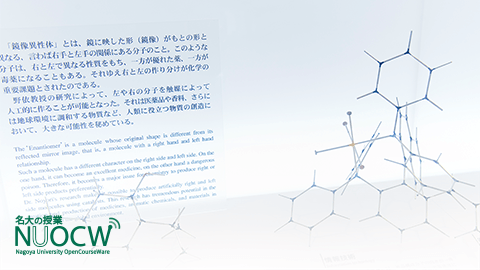
ランドスケープの保全生物学
環境学研究科
夏原由博 教授
最終更新日: 2021-12-08T14:13:55.949Z
環境学研究科は、地球環境科学専攻(主として理学の分野)、都市環境学専攻(主として工学の分野)、社会環境学専攻(主として人文・社会科学の分野)によって構成される文理融合型の研究科です。2001 年に創設されてから、既存学問分野の専門教育において研究成果を出すように日々努力しながら、地球環境問題に取り組むために、上記の異なる分野をつなぐ「環境学」を体系化する教育・研究を実施してきました。
地球環境問題とは、産業革命以降、地球システムに対する人類の活動が無視できなくなったことで生じた問題です。このような地球環境問題に対して、環境学研究科では「持続性学」と「安全・安心学」の理念を掲げて、研究教育に取り組んでいます。「持続性学」は、長い時間スケールと広い空間スケールから、これまでの歴史を振り返り、人新世の今を生きている我々が将来のために何ができるのかを考えるための視点です。一方の「安心・安全学」は、自然災害に脆弱な地域、汚染物質と隣り合わせで住む人々、また急激な都市化や過疎化で変化する地域社会など、ローカルな地域が抱える問題をグローバルな問題と関係させながら考える視点です。地球環境問題を俯瞰的に考える「持続性学」と人や地域から考える「安心・安全学」は、相互に関係し合っており、どちらか一方ではなく、両方を総合的に考えていかなければなりません。
環境学研究科では、「持続性学」と「安心・安全学」を学ぶために、研究科共通科目として文理にまたがる環境問題を扱う「体系理解科目」(博士前期課程)および「研究科共通科目」(博士後期課程)を複数提供しています。専門科目やセミナーで既存学問分野の知識を深化させながら、「体系理解科目」と「研究科共通科目」を修めることで、地球環境問題の解決に必要な総合力を養成します。さらに、国際的な環境リーダーを育成する「国際環境人材育成プログラム(博士前期課程)」、フィールドワークを実施して地域問題の解決策を提案する「統合環境学特別コース(博士後期課程)」、そして社会人が現職のまま大学院に入学し、環境学研究科が有する様々な研究リソースやネットワークを利活用しながら環境問題の解決に取り組んで学位取得を目指す「知の共創プログラム(博士後期課程)」など、多様な学生のニーズに合わせた教育と研究の場を提供しています。これらの研究教育は、研究科の枠を超えて、学内の「減災連携研究センター」、「名古屋大学博物館」、「フューチャーアース研究センター」、「未来社会創造機構・脱炭素社会創造センター」とも連携しながら行われています。
私たちは、既存学問分野の研究を極めるとともに、学問分野の枠を超えて、地球環境問題を解決するリーダーとして活躍できる皆さまと一緒に、研鑽を積み、また切磋琢磨し、新しい「環境学」の創造にチャレンジしていきたいと思っています。

体系理解科目「環境学フィールドセミナー」での藤前干潟の訪問。干潟に入り、生物相などを実際に見てみる。柔らかい泥が、足の裏に心地良い。

体系理解科目「環境学フィールドセミナー」での風力発電施設の訪問。豊田通商の方から風力発電の現状と今後の見通しなどを伺う。
環境学研究科長 横山智 教授
環境学研究科長の横山智教授に 5 つの質問に答えて頂きました。
環境学研究科の強み(醍醐味)を教えてください。
国内には「環境学」もしくは「環境科学」と銘打った大学院が数多くありますが、名古屋大学大学院環境学研究科は、その中で最も早く設立され、また協力教員を含めると 130 名を超える教員が在籍しており、規模も国内では最大級です。また、環境問題の解決、地球環境と調和した新しい人類社会をめざすために、環境をテーマとする異なる学問分野が連携して、真の文理融合の教育研究を実施していることが強みです。
研究科の教育カリキュラムの特徴は、それぞれの専攻が提供する専門科目と並び、専攻にとらわれずに環境学に必要な知識を学ぶ研究科共通科目が用意されていることです。加えて、環境学研究科独自の教育プログラムも提供しています。1 つ目は、都市環境学専攻持続発展学系の博士前期課程では、特色ある体系的な教育を英語で実施する「国際環境人材育成プログラム(NUGELP)」、そして 2 つ目は、地域の環境問題を発見し解決の道筋を提案する博士後期課程の「総合環境学特別コース」です。さらに、社会で具体的に環境問題と向き合っている社会人の方々を対象とした博士後期課程の「知の共創プログラム特別コース」を 2022 年度から開始しております。
研究面でも文理連携を進めています。2021 年度より「地球規模課題 10 課題」を選定し、研究科内の異なる分野の複数の教員が世話人となり、多様な環境問題を理解するためのシンポジウムやエクスカーションを実施しております。
自らの専門分野を超えて、グローバルな地球規模からローカルな地域規模にわたる環境問題を俯瞰できる広い視野と問題解決に取り組む能力を身につけることができる国際的にもユニークな大学院を目指して、常に新しい取り組みにチャレンジしています。
環境学研究科の学生に大学生活を通じてどんな風に育って欲しいですか。
環境問題と言っても、地球規模の温暖化や海洋汚染から、集落規模の人口減少であったり獣害であったり、そのスケールは様々です。また環境問題の多くはステークホルダーの利害が複雑に絡み合うため、その解決には合意形成が必要となります。
そこで、私たちはいつも学生のみなさんに「専⾨を持ったジェネラリスト」、「異分野を理解できるスペシャリスト」になってくださいと伝えています。「専⾨を持ったジェネラリスト」とは、グローバルな視野を持ち、ローカルな地域の持つ学術的価値を社会的・経済的・⽂化的価値に転換できる独創⼒を有したジェネラリスト指向の⼈材です。一方の「異分野を理解できるスペシャリスト」とは、多様なステークホルダーと利害調整を行う対話⼒を持ち、飛び抜けて⾼度な専⾨知識を有したスペシャリスト指向の⼈材です。
こうした人材になるためには、専門とする学問分野を徹底的に学ぶだけではなく、自分と異なる立場、異なる意見を持った人たちを理解して、様々な人々と協力して仕事をするための広い視野を身に付けなければなりません。そこで研究科では、博士前期課程の 2 年間での学びだけでは足りないので、博士後期課程への進学を大学院生のみなさんに進めています。
環境学研究科のビジョンを教えてください。
環境学研究科は、理学、工学、人文・社会科学の異なる専門分野(縦糸)を「持続性学」と「安心・安全学」の 2 つの理念(横糸)でつなぎ、新たな学理「環境学」を構築することを使命としています。
また、学問分野の枠を超えて、地球環境問題を解決する国際的なリーダーとして活躍する人材の育成を目指します。環境学研究科の大学院生の約 4 割は海外からの留学生で、授業やセミナーの多くは日本語と英語の両方で開講されています。また、研究科には「国際室」が設置されており、日本人の学生と留学生との交流イベントを積極的に実施しております。専門分野の習得だけでなく、異文化を理解した国際人材を育てるための国際化も積極的に進めております。
横山先生ご自身が学生だった時、印象的な授業はありましたか。
大学院生の時の「野外実験」が印象的です。私の専門は地理学で、大学院生と教員の計 20 名ぐらいで、調査地に 1 週間泊り込みのフィールドワークを年に 2 回実施しました。大学院生は毎年必ず参加しなければなりませんでした。朝から調査に出て、夕方までには宿に戻り、夜はミーティング。そして、毎晩ミーティング後は飲み会というものでした。飲み会といっても、若手の助手や講師の先生からのアドバイスでしたので、飲み会の時間も重要な意味を持っていました。
この野外実習で地理学のフィールドワークの基礎、どこに行けばどんな資料が得られるかなど、多くのことを学び、それが現在の研究でも活かされています。
環境学研究科への入学希望者に向けてメッセージをお願いします。
環境学研究科では、理学領域、工学領域、そして人文社会領域のそれぞれの学問を大学院でより追求したい学生はもちろん、理系だけど文系の考え方も学びたい、文系だけど理系の研究手法にも興味があるといった学際性を身に着けたい学生を歓迎します。そのための整った教育研究環境を提供しておりますので、ぜひ、私たちとともに環境学を学んでください。
(令和 5 年 5 月 25 日)