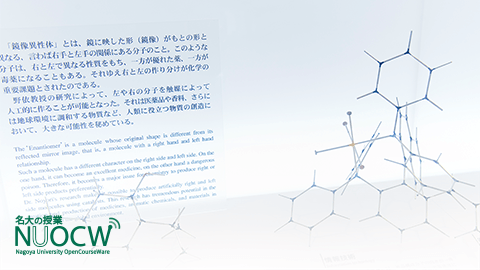
信頼性工学に魅せられて… to be continued
環境学研究科
森 保宏 教授
最終更新日: 2025/05/12
環境学研究科は、地球環境科学専攻(主として理学の分野)、都市環境学専攻(主として工学の分野)、社会環境学専攻(主として人文・社会科学の分野)によって構成される文理融合型の研究科です。2001 年に創設されてから、既存学問分野の専門教育において研究成果を出すように日々努力しながら、地球環境問題に取り組むために、上記の異なる分野をつなぐ「環境学」を体系化する教育・研究を実施してきました。
地球環境問題とは、産業革命以降、地球システムに対する人類の活動が無視できなくなったことで生じた問題です。このような地球環境問題に対して、環境学研究科では「持続性学」と「安全・安心学」の理念を掲げて、研究教育に取り組んでいます。「持続性学」は、長い時間スケールと広い空間スケールから、これまでの歴史を振り返り、人新世の今を生きている我々が将来のために何ができるのかを考えるための視点です。一方の「安心・安全学」は、自然災害に脆弱な地域、汚染物質と隣り合わせで住む人々、また急激な都市化や過疎化で変化する地域社会など、ローカルな地域が抱える問題をグローバルな問題と関係させながら考える視点です。地球環境問題を俯瞰的に考える「持続性学」と人や地域から考える「安心・安全学」は、相互に関係し合っており、どちらか一方ではなく、両方を総合的に考えていかなければなりません。
環境学研究科では、「持続性学」と「安心・安全学」を学ぶために、研究科共通科目として文理にまたがる環境問題を扱う「体系理解科目」(博士前期課程)および「研究科共通科目」(博士後期課程)を複数提供しています。専門科目やセミナーで既存学問分野の知識を深化させながら、「体系理解科目」と「研究科共通科目」を修めることで、地球環境問題の解決に必要な総合力を養成します。さらに、国際的な環境リーダーを育成する「国際環境人材育成プログラム(博士前期課程)」、フィールドワークを実施して地域問題の解決策を提案する「統合環境学特別コース(博士後期課程)」、そして社会人が現職のまま大学院に入学し、環境学研究科が有する様々な研究リソースやネットワークを利活用しながら環境問題の解決に取り組んで学位取得を目指す「知の共創プログラム(博士後期課程)」など、多様な学生のニーズに合わせた教育と研究の場を提供しています。これらの研究教育は、研究科の枠を超えて、学内の「減災連携研究センター」、「名古屋大学博物館」、「フューチャーアース研究センター」、「未来社会創造機構・脱炭素社会創造センター」とも連携しながら行われています。
私たちは、既存学問分野の研究を極めるとともに、学問分野の枠を超えて、地球環境問題を解決するリーダーとして活躍できる皆さまと一緒に、研鑽を積み、また切磋琢磨し、新しい「環境学」の創造にチャレンジしていきたいと思っています。

体系理解科目「環境学フィールドセミナー」での藤前干潟の訪問。干潟に入り、生物相などを実際に見てみる。柔らかい泥が、足の裏に心地良い。

体系理解科目「環境学フィールドセミナー」での風力発電施設の訪問。豊田通商の方から風力発電の現状と今後の見通しなどを伺う。
環境学研究科長の谷川寛樹教授に 5 つの質問に答えていただきました。
名古屋大学大学院環境学研究科は、日本で初めて「文理融合型」として設立された大学院研究科であり、理学・工学・人文社会科学の多様な学問が融合する学際的な学びの場です。「地球環境科学専攻」「都市環境学専攻」「社会環境学専攻」の3専攻体制で、地球規模から地域に根ざした課題まで、幅広く取り組んでいます。
本研究科の醍醐味は、環境問題を単一の視点ではなく、複数の分野の知見を掛け合わせて俯瞰的かつ具体的に捉えられることにあります。特に「持続性学」と「安心・安全学」という2つの柱を軸に、過去を学び、現在を分析し、未来を設計する教育・研究を推進してきました。これにより、問題の背後にある構造や時間的・空間的連鎖を深く理解する力が育まれます。
環境問題は、単に知識や技術では解決できない、複雑で多層的な課題です。だからこそ、学生の皆さんに「専門性を持ったジェネラリスト」あるいは「異分野を理解できるスペシャリスト」として育ってほしいと願っています。
大学生活では、知識の習得だけでなく、自ら問いを立て、他者と議論を交わし、行動に移す力を養ってください。「体系理解科目」や「研究科共通科目」で培う文理融合の視点、「専門科目」で磨かれる深い専門性、そして研究活動を通じて得る現場との接点——これらの経験が、皆さんを持続可能な社会の推進役へと成長させてくれるはずです。もうひとつ、環境学研究科は留学生が多く、多文化理解や国際コミュニケーションなど、国際的な素養を身につける事ができます。国内/海外の垣根のない高度人材に育ってほしいです。
私たち環境学研究科が掲げるビジョンは、「地球規模課題への対応」と「新たな知の創造」です。究極的な人類の目標でもあるウェルビーイングとサステナビリティの両立を目指し、未来志向の環境学研究科を常に目指しています。
このビジョンのもと、以下のような方向性を大切にしています:
•持続性学:長期的視点と地球規模の視野で、環境問題を歴史的・構造的に捉え、 未来の選択肢を探る。
•安心・安全学:地域や人々の生活に寄り添い、自然災害や健康リスクといった具体的な課題に実践的に対処する。
•高度人材の育成:修士・博士課程を通じて、イノベーションを牽引しうる博士人材の輩出に力を注ぎます。
このように、「知を統合し、実践へとつなげる」ことを重視しながら、環境と人間の共生を支える教育と研究に邁進しています。
私自身、学生時代は決して模範的な学生だったとは言えませんが、そんな中でも特に印象に残っているのが「構造力学」の講義です。この講義では、建物や橋といった社会の基盤を支える構造物が、どのように安全性を確保しているのかを、数式や数値を通じて論理的に説明していきました。
何気なく使っているインフラの裏側に、見えない「安全性」がきちんと数値で表現されていることに大きな感銘を受けました。そして、サステナビリティや安全性といった概念も、抽象的に語るだけでなく、しっかりと定量的に把握し、裏付けをもって考えることが重要であるということに気づかされました。
この経験は、現在私が取り組んでいる研究にも大きな影響を与えています。今は「都市の体重測定」とも呼べるような研究を進めています。都市に蓄積された建築物やインフラ、製品などの資源の質量を測定し、それを通じて社会経済における物質の流れ、いわゆる「物質代謝」を定量的かつ面的に捉えることで、持続可能性の観点から都市や社会のあり方を分析・提言するものです。
何気なく受けた学生時代の一つの講義が、後の研究や問題意識の原点になることもあります。構造力学の講義は、私にとってまさにそのような原点の一つでした。
環境学は、未来社会の設計図を描く学問です。気候変動、生物多様性の損失、災害リスク、都市と地方の不均衡、資源循環……そのどれもが、私たちの生き方と深く結びついています。
名古屋大学大学院環境学研究科では、こうした課題に真正面から向き合い、多様な価値観と知の交差点で学び、議論し、実践できる環境が整っています。特に博士課程教育にも注力しており、国や大学による経済的支援制度も充実しています。皆さんが安心して研究に打ち込めるよう、全力でサポートしてまいります。
持続可能な社会の実現に貢献したいという志を持った皆さんと、この学び舎で出会えることを楽しみにしています。ともに、新しい時代の環境学を築いていきましょう。
(令和 7 年 6 月 5 日)