テクスト布置解釈学原論-2008
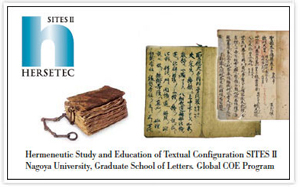
| 講師 | 佐藤彰一 教授 |
|---|---|
| 開講部局 | 文学部/文学研究科 2008年度 後期 |
| 対象者 | 文学研究科 |
テクスト布置とは
21 世紀COEプログラムの 5 年間から得られた成果の一つは、テクストが特有の布置を自ら構成するということであった。テクストが成立するプロセスの所産としての前テクスト、他のテクストとの広義の引用関係としての間テクスト性、テクストそれ自体への注釈ないしは解釈としてのメタテクスト、テクストが帰属するジャンルを明示する指標としての題名、書式、構成などのパラテクストなどがその構成要素である。こうした一連のテクスト群が取結ぶ諸関係の結節点として当該テクストは存在しており、その布置の総体が広義のテクストなのである。
講義概要、講義ノート
講義リスト
-
第 2 回 グローバル COE ガイダンス
第 1 回 担当:名古屋大学大学院文学研究科 松澤 和宏 教授(フランス文学)
授業要約
或る人の発した言葉を理解しようとするとき、どのような操作を人は「理解」の名の下に行うのだろうか?
容易に思いつくことは、外国語を学ぶときの体験に重ね合わせて「理解」という営みを考えることである。辞書の定める単語の意味や文法を通して発せられた言葉を解読しようとすることになる。しかしながら、日頃、私たちが言葉を通して他人と意思疎通をはかったり読書をしている時に、実際に生きて働いている精神の営みは、辞書や文法の埒内には到底収まらない。なぜその人はこうした言葉を発したのか、そうした問いを抱かずには私たちの解釈の営みは一瞬たりとも成立しない。仮に言い表されたことが虚言であったとしても、虚言が言い表されたという事実の裡に、表現主体の意図を忖度することになる。機械論的因果関係の説明ではなく、相手の立場に身を置いて内在的に理解しようと努めなければならなくなる。表現内容の真偽ばかりではなく、他者の意図の理解が求められる。そこに身近でありながら、形式論理によっては合理化しきれない解釈という領域が顕れてくる。自然科学とは異なる人文学の特徴の一つは、この解釈学的な営為にあると言えよう。勿論これは<テクスト布置の解釈学>に向かうほんの一歩に過ぎない。なぜなら他者の意図を内側から理解しようとするいかなる営みも、解釈主体の主観性を完全に払拭することはできないからなのである。そもそも理解に先だって、理解を促し誘導するものに私たちは常に既に囲繞されている。それを先入主と呼んでもよい。いかなる研究もこうした先入主から完全に解放されることはありえない。なぜならそれは理解をそもそも可能にする地平でもあるからである。
こうしてテクストの解釈は、発信者(著者)と受信者(解釈者)の両極を周回する ∞ の軌道を描く運動となる。言い換えれば、テクストとは二つの輪の接するところ、還元不可能な二重性として顕れてくる。一方でも他方でもないが、つねに双方に同時に関わり合うという場、形式論理では捉え難い、排中律を超えた場ならざる場として顕現してくることになるだろう。
第 3 回 担当:文学研究科 佐藤 彰一 教授(西洋史学)
授業要約
「封建制概念のテクスト論的脱構築のために」
「封建制」という用語が、歴史研究において最も重要な概念の一つであることは、誰も異論を唱えるものはいないであろう。もともとこの言葉は、西洋中世の「フューダリズム」を表現するために、中国古代の統治制度の類型を言い表す言葉から借用したものである。その制度的核芯にあるのは、主従関係形成の担保となった「封 feudum」であり、封は家臣が主君への奉仕の対価として与えられる土地その他の利益を生み出す財貨のことである。封の授受の条件や、授受の法的効力などは時代により変遷があり、これら変化を含めた多様な要素の総体がいわば「封建制度」と称されるシステムである。
こうした説明から理解されるように、このシステムの核となっているのは「封」であり、この「封」概念は11世紀から13世紀にかけて北イタリアで編纂された『封建法書 Libri Feudorum』において、初めて法概念として構築された。そして16世紀の一群の人文学者、法学者たちにより、この『封建法書』が再解釈され、現在我々が知るような形で確立した概念なのである。
やがてこの概念は啓蒙時代のヴォルテールの『習俗論』や、モンテスキューの『法の精神』などを通じて人口に膾炙し、1789年8月11日の有名な国民公会決議によって、歴史的な実体を具えた概念として定着した。カール・マルクスがこの概念を彼の歴史理論に巧みに取り込んで、世界史発展の基本法則を構築したことはよく知られている。それ以後、この概念が中世という時代を性格づける上で、なくてはならないものとなった。
だが翻って、『封建法書』以前に「封」の概念を用いた中世の人々が、果たして『封建法書』において13世紀の法学者たちが定義したような意味で「封」を理解したか否かは、実はそれほど自明とは言えないのである。
今回の講義は、封建制概念の生成に関する問題の所在と今後の研究の展望を示すに止め、『封建法書』の分析を手始めに、今後研究の進展に即して解明された問題を講ずる予定である。
第 4 回 担当:経済学研究科 長尾 伸一 教授(経済学史)
授業要約
「思想史研究とマニュスクリプト − スコットランド哲学研究をもとにして」
本講義では 18 世紀スコットランドの哲学者トマス・リードを取り上げ、コンテクスト 主義や言語行為論の観点を踏まえて、18 世紀のマニュスクリプトを言説として考察し た。
いまだ高価で,多くの「学術的」な著作は予約購読の形で流通したとはいえ,書物はもっとも広い受け手に向かって発信された公的言説だった.それに加えて大学での講義もまた,教師の見解を伝える一種の「出版」と見ることができる.講義を聴いたり講義ノートを読むことは,高等教育を受けることができた少数の人々の特権だった.リードの「ユートピア論文」のような手書き原稿は,さらに限定された受け手に対して著者の思想や意見を伝達する手段だった.科学者集団が普遍的に制度化されるのは次の世紀であり,この時代でも科学者たちはいまだに「学術的書簡」によって意見交換を続けていた.書簡はまた社会的,政治的に問題のある学問的主題を仲間内だけで論じるための安全な方法であり,数学者たちでさえそのような危惧を持つことがあった.
特権的な少数者のために製作され,流通したとはいえ,以下のような理由で,これらはすべて「公的言説」とみなすことができる.それらの言説が発話され,書かれ,伝達された空間は親族や友人たちで構成される「親密圏」ではなかった.これらの言説がその内部に存在した空間を構成する団体やネットワークへの参加者たちは,文芸や科学研究や政策形成のような,何か重要な,何か社会にとって有益な,言い換えれば何か「公的」な活動に自分たちがかかわっていると考えていた.その空間の中では彼らは私人ではなく,一種の「公人」として振舞っていたのである.
このように 18 世紀のマニュスクリプトを言説として研究することは,それらの資料の内容だけでなく,同じ著者による印刷物の性質にも光を当てることになる.以上の議論は 18 世紀の言説の多様性を明らかにするので,当然「書物とは何か」,あるいは「書物」を書くという行為の意味と意図とは何かということが次に問われるからである.テクストは自らの創造者の期待や戦略とは関係なく,それ自身の物語を語り出していく.しかしそれはまた言語行為の産物でもある.何かを「書く」という行為の最初には,それを始動させる誰かの欲望がある.要するに,「古典」と呼ばれる膨大な紙片の集積の背後には人間存在が立っている.18 世紀のテクストを言説としてとらえることは,テクスト性とともにコンテクストも無視できないことを想起させる.そしてこの両者の結びつきの探求は,歴史学と思想史と批評理論の思いがけない出会いを準備する.政治言説史の方法に関する J.G.A.ポーコックの表現[i]をパラフレーズするとすれば,それが可能なことこそが,18 世紀ブリテンに代表される初期近代の西欧社会の一つの特徴を指し示しているのである.
第 5 回 担当:文学研究科 阿部 泰郎 教授(比較人文学)
授業要約
「中世宗教テクストの地平」
日本の中世の宗教テクストの重要なコレクションである大須観音(真福寺)の蔵書に関して、神道テクストが、もっと大きな座標のもとで改めて再び位置づけられることになる、新たな発見が行われた。この報告はそのドキュメントとなる。
『太田命訓伝』は、巻子本の軸の合わせ目に「行忠」という署名があり、13 世紀後半に活躍した、度会神道という中世の新しい思想の潮流の担い手、度会行忠の自筆本であることが確認された。また、『麗気記』と総称される、共通した同様の書誌的形態・特徴を持つ一連の神道テクストの体系がある。これは、いわゆる真言神道(両部神道)と呼ばれる、仏教とくに密教と深く結びついた神道のテクストである。これらが、どのような大きな体系のもとで位置づけられるか—その決定的な資料が、『野決目録』である。
『野決目録』中の「本抄」部の冒頭にあたる『大伝法灌頂注式』の奥書には、「野決」具書(いわゆる野決—小野流の口決—に属する一群のテクスト)全体の素性を示す伝来の著者の識語がある。正和2年、宏瑜が鑁海に、文保3年、鑁海が儀海に、そして観応3年、儀海が宥恵(真福寺初代濃信の弟子)に伝授したという。『野決目録』末尾の識語を見ると、「野決」具書は、醍醐僧正=勝賢と、北院御室=後白河院皇子・守覚法親王との問答によって生み出されたテクストであることが記しづけられている。
真言密教の流れは、広沢流と小野流の二つに大別される。醍醐寺を拠点として、小野流の中心をなしていたのが三宝院勝賢である。一方、守覚は広沢流に属し、法親王という特別尊貴な立場から、この両方に分裂した真言密教をひとつに統合しようという試みを展開した。これらの神道テクストは、守覚の求めによって勝賢が、小野流(その中でも三宝院流)の秘密をことごとく明かす—口決伝授のプロセスのもとで、次々と明かされていった秘密をテクスト化した書物であることがわかる。ひとつの大きなテクスト宇宙を形作った、守覚法親王という偉大なテクスト作成者の営為の一端として認知できるという意味でも、この「野決」具書群は画期的なテクスト布置の所産と認められるのである。
第 6 回 担当:文学研究科 釘貫 亨 教授(日本語学)
授業要約
慶応2年1866、徳川幕府の官僚である前島密が将軍徳川慶喜に建白した「漢字御廃止之儀」は、極めてラジカルな国字改革として知られる。この改革案が結果的に実現しなかった原因は、様々に考えられるが、その大きな要因として、当時の庶民の漢字を巡るリテラシーの高さが障害となったことは確実である。幕府や各藩が百姓、町人の教育に責任を持ったことはないが、寺子屋などの民間の教育機関が庶民教育を担った。本来、支配者の専有物であった文字とりわけ漢字の民衆への下降は、鎌倉時代に仏教僧侶を媒介にして始まり、近世期には大衆的出版物が漢字情報を民衆に普及する役割を果たした。当時の大衆的な読み物に使われる漢字には、出版書肆の配慮で音訓にわたる極めて懇切な振り仮名が施されており、これが教育的効果を持ったことが容易に想像される。近世期には商業活動や農業経営において文書決裁が常態化しており、これに従事する農民や商人にとって文字処理能力は必須の要諦であった。寺子屋の普及は、このような社会的要求に応えたものであった。幕末には、人力車夫や大家に奉公する少女が労働の合間に書物を読みふける光景が複数の西洋の外交官によって驚きを以て報告されており、幕末当時の日本の書記生活は、漢字なしに成り立たなくなっていた。漢字は日本人にとって難解な外国文字であるが、長年にわたる学習の結果、抽象的概念をこれによって表示する習慣が身についており、明治維新以後の近代化過程の中で西洋の制度、思想、技術にかかるあらゆる概念を漢語訳によって乗り切ったことは、世界の近代化過程の中で特筆すべき出来事である。
第 7 回 担当:文学研究科 古尾谷 知浩 准教授(日本史学)
授業要約
「日本古代の戸籍と計帳」古尾谷知浩
本講義は、日本古代の歴史テクストのうち、中国から継受した法典である律令やその補足・改正・細則である格式などの法制史料群と、法の執行に伴って生成するテクストである行政文書群の布置構造を検討することを目的とした。具体的には、民衆支配の問題を取り上げ、戸令や賦役令の諸規定の構成、戸籍や計帳の作成手続を解説した。それを踏まえた上で、特に死亡者の取り扱いを、法規定や戸籍・計帳の草案への書き込みなどから分析し、実態の変化が行政文書にどのように表現され、それが法規定にどのように反映されることになったのかを明らかにした。以上のことから、法制史料と行政文書が、実態としての社会の変化の中で双方向的に影響を与えていたことを示した。
第 8 回 担当:文学研究科 和崎 春日 教授(比較人文学)
授業要約
「テクストを読み取ること」を、時間軸をいれて「読み取れる意味の変化」として捉えていく動態的な意味の読み取り方法論を提案する。まず、日本で社会化・文化化された私が、そこの価値基準を知らないアフリカを始めて訪れ、徐々にその生活様式に慣れていく変化を、「テクスト動態」として取り扱う。こうテーマを設定することによって、刻々と変わっていくテクスト間の布置関係が動態的に把握できるからである。
異文化に住み始めた文化人類学者は、始めのうち、自分が慣れ親しんだコンテクスト − テクスト関係による意味の読み取りを試みるしかない。そこのコンテクストもテクストもまったくわからない。言葉の一つ一つを獲得していき、ある物ある事の意味を教わると、生活事象全般の意味が一つ一つ明らかになっていき、自分が知りたい事象の意味(たとえばある儀礼の意味)の一端が見えてくる。この間、何回もの読み間違いと齟齬と誤解(相互の)とタブー侵犯をおこなう。周りの事象の意味が一つずつわかると、ある対象とする特定事象の意味も段階的にわかってくる。その事象が見えてくると、周りの意味も以前とはまったく違うものに見えてくる。これを、何度も何度も、毎日毎日繰り返す。
こうして、単なる静態的なテクスト変換の布置ではなく、このように時間軸をいれて刻々とフェーズを変える「複数テクスト遷移モデル」が人々の行為や物事の「読み取り」には、枢要であることを提案する。しかも、このモデルは、コンテクストとテクストの地位逆転可能性を包摂したモデルである。つまり、生活にある物事の意味は、主役になって注目され意味を読み取られるが、逆にそれが脇役になって他の事象の意味を規定する。こうして、「コンテクスト − テクストの相互変換性」を包摂した「複数テクスト遷移モデル」の有効性を提案したのである。
第 9 回 担当:文学研究科 重見 晋也 准教授(電子テクスト学)
授業要約
近代以降特に文学テクストにおいては作者にテクストを帰属させ,活版印刷以来の大量生産技術を用いて同一のテクストを大量に流通させることで,テクストの同一性を保ってきた.しかし,ロラン・バルトが「作者の死」を宣言すると,聖ヒエロニムス以来堅持されてきたテクストを作者に帰属させるという考え方が大きく揺らぐことになった.すなわち,テクストの価値・整合性・文体的均一性・時間的整合性という 4 つの基準はもはや無用のものと考えられるようになったのである.
本来テクストは同一のテクストであれ異なるテクストであれ,その価値や形式は時代やメディアにあわせて変化していくものである.そうであれば,デジタル・テクストの時代を迎えてテクストがどのようにして自らの同一性を確保しうるのかを考えることは,テクスト概念の現在を考えることに他ならない.デジタル・テクストの例としてハイパーテクストを実装した Web を対象に考えると,テクストとしての Web は空間性,物質性,時間性の 3 つの点で自己同一性を実現していることが分かる.デジタル・テクストにおける自己同一性の実現は,フーコーが『知の考古学』で述べた,言表が言説を構成する際に相関する 3 つの領域に一致している.
第 10 回 担当:文学研究科 フォヴェルグ外国人教師(フランス文学)
授業要約
ライプニッツとディドロにおける記号論の問題
17 世紀と 18 世紀にロックやライプニッツやディドロなどの著作者に定義されてきた記号論は、言語記号以前の記号の概念に属して、その考案の様々な特徴に参考する値がある。と言うのは、記号論の問題は解釈の観念に関係する。ライプニッツによると、記号論は人間の持っている秩序と技術の認識と発明の能力に係わり、外界に意義を与えるという能力に係わる。
ところで、我々は外界の秩序は直ちに感知できず、現象の理解は現れてくる現象に与える秩序に依り、つまり知覚が立つ秩序に依る。従って、知覚は記号論にモデルを示す。というのも、知覚そのものは感性のできる質と抽象的な概念を混合している。その点において、別の面では一致しない著者でもあるライプニッツとディドロが同意する。どの感覚器官にもタブラ (tabula、ラテン語)が備えていて、そのタブラによって一々の感覚と言語以前の記号を組み合わせられる。
そういうことで、記号論は、最初に同一視された論理学と区別され、発明の技術としてライプニッツに定義されて、更に百科全書の計画において最適な応用を受ける。なぜなら、18 世紀にディドロとダランベールが編集した百科全書は、発明と発見の偶然な秩序に従って科学と技術の歴史を記述するだけでなく、むしろ記録される様々な知識の秩序自体が発明の方法を示すことを望んでいる。言い換えれば、発明の技術を知るには、発見の歴史は役に立たない。結局は、実際に科学的で百科全書に適切な秩序を定めるために記号論が必要になる。なぜなら、百科全書派に考案される記号論は、現象の秩序と知覚の秩序の関係を複数の類似に基づく関係であることを認識して、その類似は当然でないことであって、絶えずに確認する必要があることを認識している。
第 11 回 担当:文学研究科 高橋 亨 教授(日本古典文学)
授業要約
物語テクストの絵と歌について
『源氏物語』や『狭衣物語』などの平安朝の物語作品においては、その生成の過程から絵や歌との密接な関係がある。画中に複数の場面をもつ屏風絵においては、そこに画中の人物に同化した内部の視点から、また、その場面を外部の視点から対象化した屏風歌が詠まれている。それらを連続的に結合すれば、歌を伴った物語が生まれる。あるいは、歌絵とよばれるような小画面の紙絵においては、それらを複数組み合わせて配列することによって、やはり歌を伴った物語が生成する。そうした文献記録はあるが、平安朝中期までの実作品は、ほとんど現存していない。
現存するのは、徳川・五島本の『源氏物語絵巻』など、平安朝後期から江戸期に至る「源氏絵」などの物語絵であり、それらは文字テクストの享受によるものである。その享受においては、歌や詞書を伴わない絵のみの絵画化や、絵を伴わない歌のみを採録したテクストも生成している。
本講義においては、こうした平安朝物語における絵と歌と物語テクストとの関連について概括するとともに、『源氏物語』と『狭衣物語』の絵画資料を具体例として、その歌との関わりについて考察した。特に、『狭衣物語』の絵画資料に関しては、従来は鎌倉時代の絵巻断簡と承応版本の挿絵のほかは、ほとんどその存在が知られていなかった。それら『狭衣物語』の現存絵画資料を紹介し、それに基づいたテクスト論の可能性を探った。
第 12 回 担当:文学研究科 天野 政千代 教授(英語学)
授業要約
発話の内容である命題(proposition)に対する話し手や書き手の心的態度を法性(modality)といい、直説法、仮定法、命令法のように法性を表すために特殊化された動詞の屈折語尾形態を法(mood)という。言語では法性は法によってのみ表されるのではなく、法助動詞、準法助動詞、法副詞、挿入節などいくつかの語彙的手段によっても表される。しかし、現代英語の will, may, shall, must 等の方助動詞は語彙的項目というよりは、法性を表すために特殊化された項目であり、機能的項目と一般に見なされている。法性を表現するために特殊化された屈折語尾形態や機能的項目の存在は早くから文法家の関心を集め、様々な研究がなされてきた。
絵画のような非言語テクストも描かれた対象に対する画家の心的態度を表すことは言うまでもなく、特に人物や生き物の目と法性との強い関係が体系・機能文法の研究者によって近年指摘されている。法性は目のみによって表されるのではなく、色彩、構図、被書体の大きさなどによっても表されるが、目は法性を表現するために特殊化された器官と言うことができるであろう。今回の授業では、北信濃の小布施市にある岩松院の本堂天井に葛飾北斎によって描かれた鳳凰図を取り上げ、この絵の法性について論じた。鳳凰が架空の生き物であるという事実が、法性を強める結果になっていることを見逃してはならないが、その八方睨みの目として知られる目と法性の強い関係は特に注目に値する。この目の異様な鋭さは法性そのものであり、見る者に特殊な印象を与えるため、すでに言語の法に対応するものと言うことができる。
講義ノート
第 9 回 担当:文学研究科 重見 晋也 准教授(電子テクスト学)
成績評価
レポート課題を課す。
レポート内容:授業で扱われた内容を自分の課程博士論文計画と連動させて論じなさい
投稿日
May 15, 2020