国際政治学
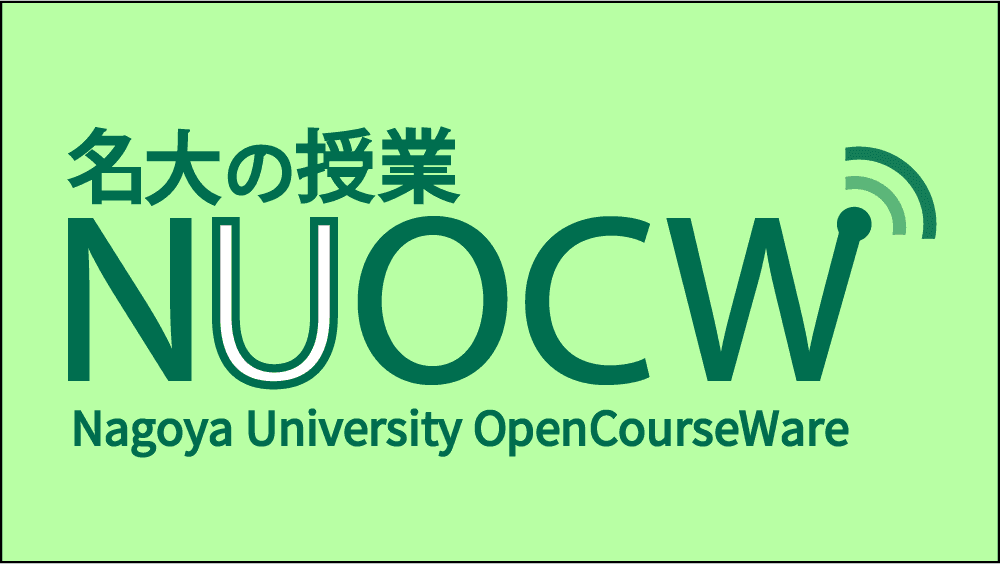
| 講師 | 三浦 聡 教授 |
|---|---|
| 開講部局 | 法学部/法学研究科 2025年度春学期 |
| 対象者 | 法学部3・4年生 |
授業の目的
本授業は、国際政治の現実と理論を踏まえつつ、大局的見地に立ってものごとを理論的・戦略的・戦略的に判断する能力を養うことです。
日本、アメリカ、中国などの外交をはじめとする国際政治に関心を持っていても、それらをどう読むかは難しいと感じる人は多いかもしれません。本授業は、そのような受講者を対象として、国際政治について、単なる感情や感想を越えて学術的に分析する能力を養います。
到達目標
本講義の到達目標は以下の3点です。
- 国際政治とグローバル・ガバナンスへの関心を高め、関連する新聞記事や資料を受講前よりも深く読める。
- 国際政治とグローバル・ガバナンスについての一定程度の知識と分析能力を身につける。
- 卒業後を見据え、ディスカッションや共同作業に慣れる。
以上の目標を踏まえ、本授業では受講者によるグループ・ディスカッションとグループ・ワークを取り入れます。
授業の工夫
本授業における主な工夫として、以下の2点が挙げられます。
第1に、一方的な講義を極力避けて、受講者によるグループ・ディスカッションとグループ・ワークを多く取り入れています。まず、学期を通じてできるだけ多くの受講者とディスカッションができるように、1グループを4~5名として、毎回ランダムにグループを編成しています。つぎに、特定のテーマについてできるだけ深い議論ができるように、事前に課題を課し、課題に対する全員の回答(個人情報を削除したもの)をまとめたファイルを受講者全員とシェアしたうえで、グループ・ディスカッションに臨んでもらっています。これにより、受講者が多様な考えにふれつつ学び合う「ピア・ラーニング」が促されます(優秀な学生は本学にとって最も貴重な財産の一つであり、これを最大限に活用しない手はありません)。さらに、グループ・ディスカッションが向かう方向を定めるために、事前課題を発展させたグループ課題を課し、各グループが授業時間内にアウトプットを提出するというグループ・ワークを行っています。本授業で以上の形式を採用しているのは、受講者の将来を見据えると、グループでのプロジェクトを円滑に進める諸能力の向上が必要だと考えているからです。
第2に、グループ・ディスカッションとグループ・ワークを通じて、受講者に「探究の姿勢」を意識してもらっています。「探究の姿勢」のうち、本授業でとくに強調しているのが、「問いを投げかける」、「分析的に考える」、「複眼的に考える」、「核心をつかむ」、「具体と抽象を往復する」、「点と点をつなぐ」という6つの姿勢です。これらを「姿勢」と呼ぶのは、当初はこれらを繰り返し意識しつつも、将来的には無意識のうちに実践できるよう身につけてほしいという意味を込めているからです。ただし、スポーツなどのフォームと同様に、「探究の姿勢」を身につけるためには日々のプラクティス(実践と反復練習)が欠かせず、本授業に参加するだけでは不十分であることも強調しています。6つの姿勢のうち特に重視しているのが「分析的に考える」姿勢であり、その実践を促すために、受講者に様々な分析フレームワーク(枠組)を示し、使ってもらっています。本授業ではまた、「探究の姿勢」は単に学生として必要なだけでなく、受講者が市民、有権者、ビジネスパーソン、公務員、消費者など様々な役割を担う際にも大事だと伝えています。
本授業はこれらを含む様々な工夫をこらしつつ、より良い授業を目指して試行錯誤を続けています。
授業の内容や構成
【内容】
本授業の目的と目標を達成するためには、 国際政治学の様々な概念や理論を理解するだけでなく、それらを使って現実を実際に読み解くことも必要です。調理器具についての知識をいくら得ても、実際に調理がうまくなるわけではありません。本授業は、教員が国際政治の様々な食材(国際政治のできごと)と道具(理論、概念など)とを示して、受講者がそれを自分なりに調理できる(分析できる)ことを目指します。
【構成】
本授業の構成は以下を予定していますが、現実の動向等を踏まえて変更する場合があります(下記「授業開講形態等」も参照のこと)。
1.イントロダクション:国際政治をどうとらえるか?
2~5. 「ポスト・ウクライナ」の国際政治
・ロシアによるウクライナ進行の現状・原因・影響等について考察します。
6~8. 米中関係の国際政治
・米中関係(米中の対立と協力)の現状・原因・影響等について考察します。
9~12. 気候変動のグローバル・ガバナンス
・パリ協定以降の気候変動のグローバル・ガバナンスについて考察します。
13~15. 持続可能な開発のグローバル・ガバナンス
・持続可能な開発について、とくに「持続可能な開発目標(SDGs)」に焦点を当てつつ考察します。
シラバスのアップデート版を初回の授業でお知らせします。
履修条件・関連する科目
本授業の履修条件はありません。本授業は、視野をさらに広げ、能力をさらに高めたい学生に向いており、単位を楽に取得したい学生や担当者の講義を聞くだけの授業を求める学生にはまったく向いていません。
評価方法と基準
・方法:平常点により評価します。平常点には、①課題の提出、②授業への参加(グループ・ディスカッションやグループ・ワークへの積極的参加)、が含まれます。ただし、諸事情により変更を加えることがありえます。
・基準:①国際政治学の基本的概念・理論を理解し、それを用いて国際政治を分析することができること、②グループ・ディスカッションに積極的に関わったことを合格の基準とします。
教科書・テキスト
必要に応じて授業内で指示します。
さしあたり、「参考書」欄に記載した「国際政治学の教科書」を参照して下さい。
参考書
・本授業の内容に関係する新書として、たとえば以下があります。
高坂正堯『国際政治――恐怖と希望』中公新書、1966年(改版2017年)。
中西寛『国際政治とは何か――地球社会における人間と秩序』中公新書、2003年。
細谷雄一『国際秩序――18世紀ヨーロッパから21世紀アジアへ』中公新書、2012年。
詫摩佳代『人類と病――国際政治から見る感染症と健康格差』中公新書、2020年。
益尾知佐子『中国の行動原理――国内潮流が決める国際関係』中公新書、2020年。
蟹江憲史『SDGs(持続可能な開発目標)』中公新書、2020年。
・国際政治学の教科書としては、たとえば以下があります。
多湖淳『国際関係論』勁草書房、2024年。
村田晃嗣ほか『国際政治学をつかむ【新版】』有斐閣、2015年。(初学者向け)
山田高敬・大矢根聡編著『グローバル社会の国際関係論』有斐閣、2011年。(初級者向け)
鈴木基史『グローバル・ガバナンス論講義』東京大学出版会、2017年。(中級者向け)
中西寛・石田淳・田所昌幸『国際政治学』有斐閣、2013年。(中級者向け)
・国際政治学の古典としては、たとえば以下があります。
中江兆民『三酔人経綸問答』岩波文庫、1965年(原書1887年)。
E・H・カー(原彬久訳)『危機の二十年――理想と現実』岩波文庫、2011年(原書初版1939年)。
モーゲンソー(原彬久訳)『国際政治――権力と平和(上・中・下)』岩波文庫、2013年(原書初版1948年)。
課外学習等
授業時間外学習用の「読み物」を適宜指示します。
注意事項
本授業は、国際政治の最新動向や受講者の反応などを踏まえて授業の内容と形式を柔軟に組み立てる余地を残しています。
本授業では、講義内容をまとめたレジュメを配布しません。課題に取り組むために必要な資料を適宜アップロードします。
授業開講形態等
本授業は、担当者による一方通行的な講義を最小限におさえ、代わりに受講者が授業中に課題をこなしてグループ・ディスカッションやグループ・ワークを行うことをメインとします。

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
投稿日
July 23, 2025
