社会学演習(アーレント『活動的生』を読む)
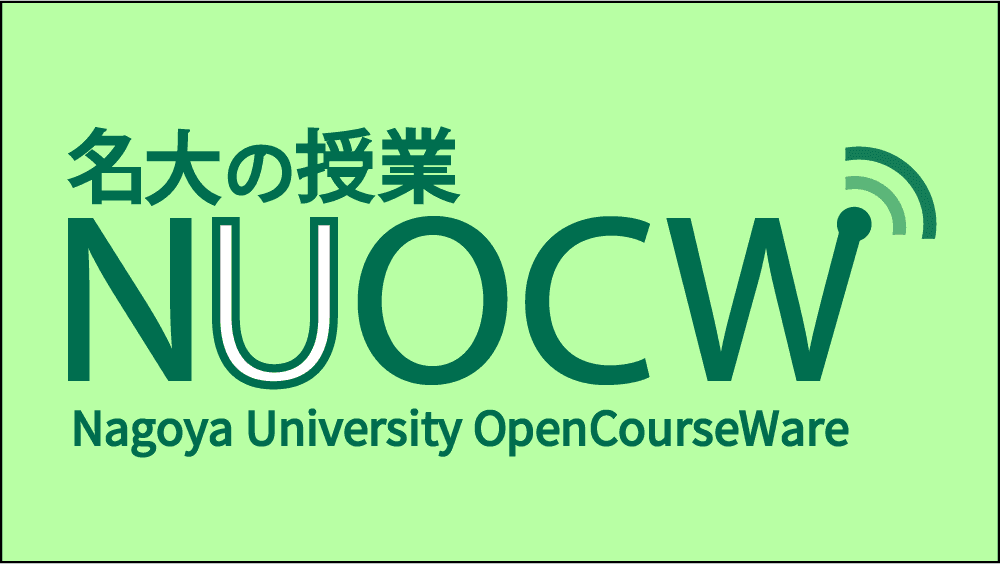
| 講師 | 上村 泰裕 准教授 |
|---|---|
| 開講部局 | 文学部/人文学研究科 2022年度春学期 |
| 対象者 | 文学部2〜4年生 |
タグ
授業の目的
ハンナ・アーレント(森一郎訳)『活動的生』(みすず書房、2015 年)をめぐる素人談義です。専門的読解も大事ですが、アーレントの議論は私たちの人生や社会について深く考察しているので、学生だけでなく社会人の皆さんにも触れていただきたいものです。
授業の工夫
コロナの副産物は、授業やゼミを録画するようになったことでした。従来ゼミは喋りっぱなしで、翌日には何を喋ったか忘れていたのですが、録画するとわれながら名講釈だと気づきます。ただし、「あのー」「えー」「そのー」「まあ」「なんというか」が聴きづらい。そこで学生にアルバイトを頼み、余計な間投詞を削除してもらったうえで、私のノートを付けました。繰り返し視聴すると、私自身、自分のアーレント解釈への理解が深まっていく気がします。アーレント流に言えば、相互行為であるべきゼミから、私の解説だけを抽出して制作した粉末スープのようなものですが、皆様の読書のお供として少しでも役立つなら幸いです。
授業の到達目標
社会学の議論の楽しさを友人たちと経験し、そこからヒントを得て自分自身の研究を進めたいという強い意欲が湧いてくることが到達目標です。ただし、大学の勉強に「これだけやれば十分」という限界はないので、到達目標に到達すれば十分と心得てはいけません。
授業の内容や構成
ゼミは大学教育の中心です。それは、フンボルトとともに近代大学の理念を作った哲学者のフィヒテが次のように述べている通りです。「ゼミナール。学園生活のあちこちで目に見えないかたちで行なわれているいくつもの対話のなかにあって、ある問題について学生が質問し教師が反問して、そこにはっきりしたソクラテス的な対話が成立する場である」(フィヒテ「ベルリンに創立予定の、科学アカデミーと緊密に結びついた高等教授施設の演繹的プラン」1807 年)。
教科書・テキスト
アーレント『活動的生』(みすず書房、2015 年)
講義資料
関連するウェブサイト

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
投稿日
September 08, 2023
