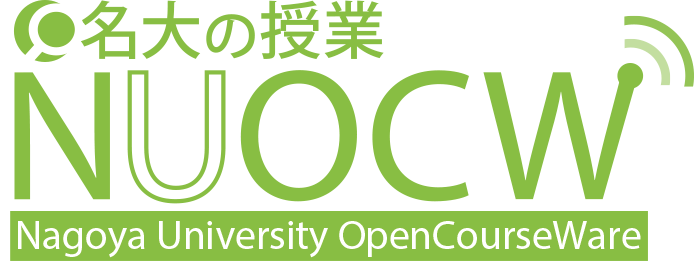美術史講義Ⅶb
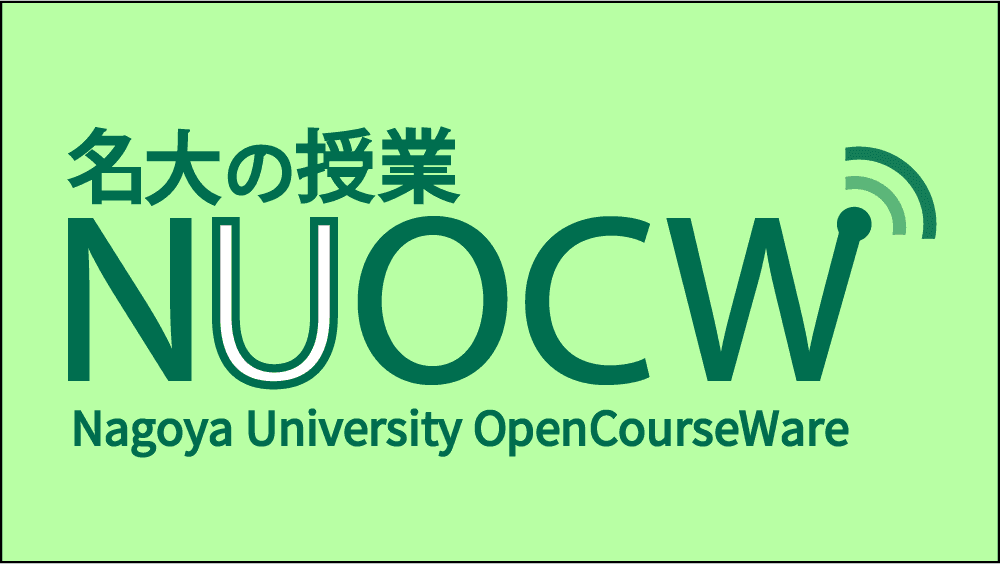
| 講師 | 伊藤 大輔 教授 |
|---|---|
| 開講部局 | 文学部/人文学研究科 2021年度秋学期 |
| 対象者 | 学部2〜4年生/院生(博士前期課程) |
授業の目的
日本美術史の専門的な内容について理解を深め、作品鑑賞力を高める。古代絵画についての知識を深める。
授業の工夫
文学が言葉を用いて作家の思考を組み立てて表現したものであるように、美術は言葉ではない視覚的な要素を用いて作家(や注文主)の思考を組み立てたものです。
美術史は歴史学の一分野ではありますが、美術品の背後にある人間の思考のあり方を情報として引き出して考察する半分哲学的でもある学問です。そのためには、イメージそのものだけでなく、イメージを具現化する物質・素材の問題、作品が作られた当時の世界観などさまざまな側面に着目する必要があります。
この授業では、古代絵画を材料に、視覚的な存在からいかに情報を引き出すかを多数の図版を用いて、ケーススタディとして示します。実際の作品を目にすることは授業内では難しいですが、受講生が旅行等で文化財に触れた際に自ら日本の文化についての学びを進めることができるよう基礎を養成することを意識しています。
到達目標
日本美術史の内、特に古代絵画という特定のテーマについて専門的知見を得て、日本の美術について自ら意見を語れるようになることを到達目標とする。
授業の内容や構成
日本美術史のうち、特に古代絵画に焦点を合わせ、主要作品について議論されている美術史上の問題と研究の状況について個別に講義を行う。また、スライドによる図版提示を数多く行い、作品分析の実践的な手法について解説する。
主として以下の話題に触れます。
- 法隆寺の成立と再建・非再建論争
- 法隆寺の絵画 1 (玉虫厨子の基本構造)
- 法隆寺の絵画 2(玉虫厨子宮殿部の絵画表現)
- 法隆寺の絵画 3(玉虫厨子須弥座の絵画表現)
- 法隆寺の絵画4(金堂壁画の基本構造)
- 法隆寺の絵画 5(金堂壁画の絵画表現)
- 法隆寺の絵画 6(金堂壁画と東アジア)
- 高松塚古墳壁画の基本表現
- 高松塚古墳壁画と東アジアの墓室壁画
- 法華堂根本曼荼羅の基本表現
- 法華堂根本曼荼羅と関連作品
- 正倉院の絵画(鳥毛立女図屏風)
- 正倉院の絵画(狩猟宴楽図と騎象奏楽図)
- 吉祥天像(薬師寺)
- まとめ
成績評価の方法と基準
主としてレポート試験により評価します。授業への参加度も 10%程度考慮します。
授業の内容の理解度、それを踏まえた上で自らの議論を展開する応用力、自らの議論を展開する為に必要な文献や作品を発掘する検索力、実作品に触れた経験の深さ、その経験を的確に言葉に直すことの出来る表現力等を総合的に判断します。
60 点以上を合格とします。
講義資料
- 著作権などに関しては、講義資料内の注意事項をご確認ください。
参考書
- 辻惟雄『日本美術の歴史』(東京大学出版会、2005 年 12 月)
- 佐藤康宏『改訂版 日本美術史』(放送大学、2014 年 3 月)
- 山下裕二・髙岸輝監修『日本美術史』(美術出版社、2014 年 4 月)
課外学習等(授業時間外学習の指示)
美術史学は教室での座学だけでは理解が十分に行き届きません。 社会的状況が許すようになった場合には、美術館・博物館・寺社等に積極的に足を運んで、実物を見る経験を積まれることを希望しております。
投稿日
October 03, 2022