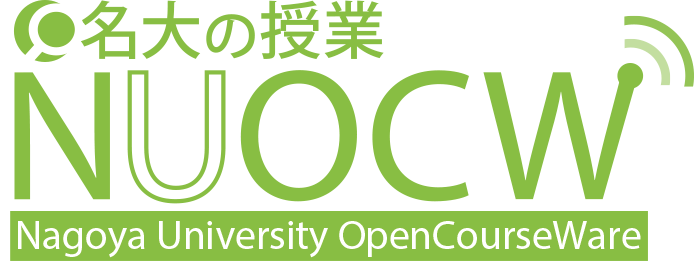すまいと環境-2018
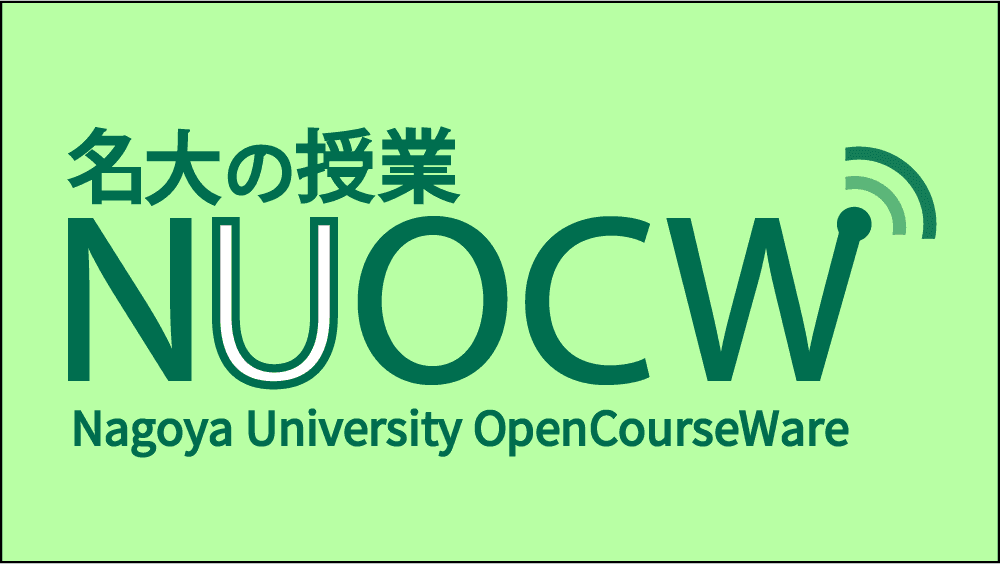
| 講師 | 久野覚 教授 |
|---|---|
| 開講部局 | 環境学研究科 2018年度 後期 |

授業の内容
「すまい」に関する歴史・意匠・計画、建築環境・設備・エネルギー、建築構造・材料の各分野から、いくつかのテーマをピックアップして講義する。
-
建築学とは
-
住宅の歴史、ライフステージ・ライフスタイル、郊外・都心居住、都市インフラ、ユニバーサルデザイン など
-
住宅の断熱・気密性能、自然・未利用エネルギー利用等の各種省エネルギー手法、熱環境・空気質環境と健康、換気、快適性、居住環境評価 など
-
建築構造システム、各種構造(RC、鉄骨、木)、構造材料・一般材料、建築生産・管理、建築廃棄物・リサイクル、建築維持・管理、耐震診断・補強・改修、防災・防火など
授業の工夫
この授業は、環境学研究科が設けている体系理解科目の一つです。環境学研究科は理工文の複合研究科であるため、環境学を構成する種々の体系について、他専攻の学生にも理解できる授業の工夫がなされています。したがって、他研究科の学生にも理解しやすく、名古屋大学6研究科連携 ESD プログラムの一つにもなっています。この授業では、建築学のエッセンスを理解してもらうことを目的として 6 人の教員によって講義をしており、私は建築環境工学について 3 回の講義を担当しています。特に、積極的な快適性、プレザントネスについて事例を交えて解説し、レポートでは身近に感じているプレザントネスについて語ってもらうことにしています。
授業の目標
「すまい」を主要な題材として取り上げ、ライフサイクルでの評価や関連法規・制度・基準などを踏まえつつ、環境学の視点から「すまい」に関連する種々のテーマを通して「建築学」の体系を理解し、応用する力を身につける。
教科書
特になし
参考書ならびに授業を受けるに当たっての注意事項等
わかりやすい空気環境の知識(健康住宅推進協議会編、オーム社)
スケジュール
- 10/2「建築学に関する概説」
- 10/9「近代都市計画」
- ピクチュアレスク庭園と都市計画への応用
- アメリカン・ボザールと都市美運動
- カミロ・ジッテと『芸術的原理に基づく都市計画』
- ル・コルビュジエとアテネ憲章
- 10/16「田園都市・田園郊外」
- 労働者階級の住宅改善と工業モデル・ヴィレッジ
- E.ハワードの田園都市構想
- レッチワースとハムステッド・ガーデン・サバーブ
- 衛星都市とニュータウン
- 10/23「日本のすまい」
- 日本の住宅の変遷
- 気候風土への適応 5 . 10/30「住まい方と住宅地」
- 日本の住宅が抱える社会的な課題
- 家族構成とライフステージ・ライフスタイル
- 郊外住宅地の現在
- 11/6「耐震構造、耐震設計の歴史と将来像」
- 地震災害と耐震基準の歴史
- 耐震構造、耐震設計の考え方
- 11/13「耐震診断と耐震改修」
- 耐震診断の考え方と方法
- 耐震改修の実際
- 被災建物の応急危険度判定、被災度判定
- 11/20「住宅構造概論」
- 住宅に用いられる種々の構造形式
- 木質構造の概論
- 建築材料としての木材
- 12/4「木造建築の歴史となりたち」
- 伝統木造構法と在来軸組構法
- 木造建築の構造としての強さ
- 12/11「木造住宅の施工」
- 施工手順の実際
- 継手・仕口、木材の接合
- 12/18「住宅の断熱・気密性能と環境性能評価」
- 住宅の省エネルギー基準
- 断熱・気密性能向上の効果と弊害
- 建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)
- 12/25「室内空気質問題とその対策」
- 室内空気汚染物質と健康被害
- 公的機関の取り組み
- 換気計画の基本
- 1/15「温熱環境と暮らし方」(久野)
- 日本の気候と室内環境
- 寒暑涼暖の違い
- 地球環境時代の暮らし方
- 1/22「居住環境評価」(久野)
- 居住環境に対する一般住民の意識
- 安心とは?
- 地球環境に対する意識と行動
- 1/29 「人間生活における環境と心理の変化」(久野)
- 様々なタイムスパンの環境変化
- 変化する温熱環境
- 空間の変化と知覚・認知
- 都市居住環境の変化
講義スライド
第 3 回「Varying Environmental and Psychological States in Human Life」
講義資料
成績評価
- 担当教員6名から課せられるレポートから、計画・構造・環境それぞれ1つ選択し、提出された3点のレポートによって総合的に評価する。総合点 60 点以上を合格とする。
- ある担当教員の講義を全て欠席した場合は、その分野(計画・構造・環境)のレポートが提出されても採点しない。もしどうしても出席が無理な事情がある場合は、予め当該教員に連絡して相談すること。
投稿日
June 15, 2020